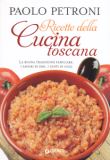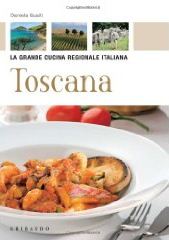「総合解説」2012年10月号の最初の記事は、“トリッパ”です。
イタリア人が大好きで、今では食通の食材とみなされているトリッパ。
これを地方料理という視点で調べ上げた、なかなか興味深い記事です。
まずは記事の追加解説をどうぞ。
ジェノヴァで(そしておそらくリグーリアで)一番古いトリッペリアと紹介されている店、ラ・カザーナTripperia La Casana。
店のショーウインドーにゆで上げたトリッパを吊るしてあるのがイタリアのトリッペリアの正しい姿。
でも、何をどう注文すればいんだか・・・。
ジェノヴァでトリッパを食べるという発想にはなかなかならないかもしれませんが、トリッパはジェノヴァの伝統料理の一つでもあります。
50年ほど前までは、トリッパのスープは朝のカップッチーノの代わりだったとか。
旧市街には、20年前は約20軒のトリッパ専門店がありましたが、今ではこの界隈に残っているのはわすが4軒だそうです。
記事にもありましたが、イタリアのトリッパ専門店は確実に減っているようです。
若者のトリッパ離れの原因は、高カロリーなイメージ、調理時間が長い、など。
でも、この店は土曜の朝には行列ができるんだそうですよ。
トリッパの主な調理方法は、アッコモダータ(またはイン・ウミド、煮込みのこと)、インサラータ、フリット。
トリッパには、4つの胃ごとに分ける方法と、ビアンカとロッソという分類の仕方があります。
アッコモダータにはトリッパ・ビアンカと呼ばれる脂肪やゼラチン質の少ない部位を使い、インサラータにはトリッパ・ロッサを使います。
ちなみに、上の店の動画で、店の奥に大鍋が2つあることが分りますが、これは、ビアンカとロッサを別々にゆでるため。
トリッパ・アッコモダータ、ジェノヴァ風
店の評判は上々のようです。
細い路地が入り組んだ旧市街にあるので、行く前に行き方のチェックをお忘れなく。
次に、トリッパのことならおまかせのトリッパアカデミーのwebページはこちら。
今日はこのくらいで。
次は、ヴェネトのトリッパ料理の話でも。
-------------------------------------------------------
“トリッパ”の記事とリチェッタの日本語訳は「総合解説」2012年10月号に載っています。
[creapasso.comへ戻る]
=====================================
イタリア人が大好きで、今では食通の食材とみなされているトリッパ。
これを地方料理という視点で調べ上げた、なかなか興味深い記事です。
まずは記事の追加解説をどうぞ。
ジェノヴァで(そしておそらくリグーリアで)一番古いトリッペリアと紹介されている店、ラ・カザーナTripperia La Casana。
店のショーウインドーにゆで上げたトリッパを吊るしてあるのがイタリアのトリッペリアの正しい姿。
でも、何をどう注文すればいんだか・・・。
ジェノヴァでトリッパを食べるという発想にはなかなかならないかもしれませんが、トリッパはジェノヴァの伝統料理の一つでもあります。
50年ほど前までは、トリッパのスープは朝のカップッチーノの代わりだったとか。
旧市街には、20年前は約20軒のトリッパ専門店がありましたが、今ではこの界隈に残っているのはわすが4軒だそうです。
記事にもありましたが、イタリアのトリッパ専門店は確実に減っているようです。
若者のトリッパ離れの原因は、高カロリーなイメージ、調理時間が長い、など。
でも、この店は土曜の朝には行列ができるんだそうですよ。
トリッパの主な調理方法は、アッコモダータ(またはイン・ウミド、煮込みのこと)、インサラータ、フリット。
トリッパには、4つの胃ごとに分ける方法と、ビアンカとロッソという分類の仕方があります。
アッコモダータにはトリッパ・ビアンカと呼ばれる脂肪やゼラチン質の少ない部位を使い、インサラータにはトリッパ・ロッサを使います。
ちなみに、上の店の動画で、店の奥に大鍋が2つあることが分りますが、これは、ビアンカとロッサを別々にゆでるため。
トリッパ・アッコモダータ、ジェノヴァ風
店の評判は上々のようです。
細い路地が入り組んだ旧市街にあるので、行く前に行き方のチェックをお忘れなく。
次に、トリッパのことならおまかせのトリッパアカデミーのwebページはこちら。
今日はこのくらいで。
次は、ヴェネトのトリッパ料理の話でも。
-------------------------------------------------------
“トリッパ”の記事とリチェッタの日本語訳は「総合解説」2012年10月号に載っています。
[creapasso.comへ戻る]
=====================================